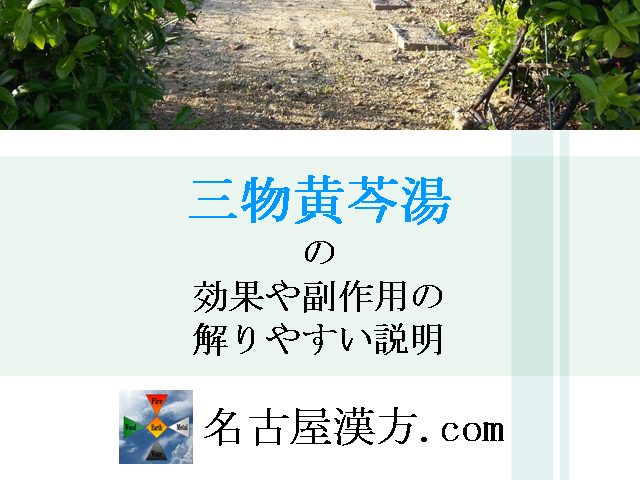
三物黄芩湯
ポイント
この記事では、三物黄芩湯についての次の事が解ります。
・患者さんへの説明方法、副作用や注意点
・出典(条文)、生薬構成
・詳しい解説、他処方との鑑別
「名古屋漢方.com」のムセキです。
本記事は、三物黄芩湯についての解説記事になります。
最初に患者さんへの説明例、その後に詳しい処方解説を載せています。日々の業務で使う資料として、ご活用頂ければ幸いです。

スポンサーリンク
<急ぎの方用>患者さんお客さんへの説明

一般的な説明
今日は、三物黄芩湯という漢方薬が出ています。このお薬は、手の火照りが酷い場合によく使われるお薬です。
今日はどのような症状で受診されましたか?
○○という症状ですね。
お困りの症状に、先生はこれが良いと考えられたようです。このお薬は、手の火照りの原因の熱を取り除いてくれますので、一度、試してみてください。
身体が冷えたり、食欲が無くなりますと効き難くなりますので、体調には充分にお気をつけ下さい。
漢方医処方の場合の説明
今日は、三物黄芩湯という漢方薬が出ています。このお薬は、手の火照りが酷い場合によく使われるお薬です。他にも頭痛や湿疹等にも使われているようです。
今日はどのような症状で受診されましたか?
○○という症状ですね。
お困りの症状に、先生はこれが良いと考えられたようです。このお薬は、身体の余分な熱を取って、手の火照りを改善してくれますので、一度、試してみてください。
身体が冷えたり、食欲が無くなりますと効き難くなりますので、体調には充分にお気をつけ下さい。
主な注意点、副作用等
アナフィラキシー
間質性肺炎
肝機能障害、黄疸
過敏症(発疹、発赤、そう痒等)
消化器(食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢等)
添付文書(ツムラ121番)
ツムラ三物黄芩湯(外部リンク)

三物黄芩湯についての漢方医学的説明

生薬構成
地黄6、黄芩3、苦参3
出典
金匱要略
条文(書き下し)
「四肢煩熱に苦しみ、頭、痛まず、ただ煩する証」
条文(現代語訳)
「手足が熱を持ち苦しみ、頭痛は無く、ただ熱を持つもの。」
解説
今日は、三物黄芩湯についての解説になります。本処方は、手足の火照りに使われています。
それでは、最初に条文を見ていきます。条文は金匱要略からの出典で、「手足の火照り」になります。
非常に短いのですが、構成生薬を見てみると興味深いことが解ります。
構成生薬は、グループ分けしますと、
補精・補腎:地黄
肺熱を清す:黄芩
下焦の伏火を瀉す:苦参
の様になっています。
面白いのは地黄と苦参の組み合わせです。これら2つの生薬で下焦の熱を取り去ります。結局、その熱が上に登って三物黄芩湯証を形成しているものと言えます。
ですのでこの処方は、腎虚となって熱を持つ「腎熱」と呼ばれる病態が原因で、肺熱を起こしている場合に使用します。
この様な状態は、腎熱がある場合はずっと続きますので、傷寒論には載らず金匱要略出典なのでしょう。この組み合わせと似たものに知母+黄柏+麦門冬があります。
知母+黄柏+麦門冬の組み合わせは後世方に多く見られ、同じ様に腎熱を取りながら肺の熱を取ります。
この辺りの使い分けは、鑑別の所で詳しくご紹介します。
所で、この処方には地黄が入っていますが、芍薬、川芎、当帰の様な補血剤が入っておりません。
これは、川芎、当帰は温性である事と、芍薬を加えたこの3生薬を加えると補血の作用に切り替わってしまう、という事が理由となります。
補血作用は、基本的に腎よりも上の部分に作用点があります。この三物黄芩湯は、その病態の中心が下焦の腎熱であるため、補腎作用が補血作用に切り替わると都合が悪い訳です。
以上、まとめますと、三物黄芩湯は「腎虚に端を発する腎熱が原因で手が火照るものに使用する処方。」と言えます。
応用的な使い方をご紹介します。心肺の熱放散は両手で行っている部分もありますので、肺熱が溜まり過ぎると火照ってきます。
本処方は、その溜まった熱が処理しきれなくて火照りとなるものを治します。ですので、証が合えば手の湿疹が酷い場合等にも使用する事が出来ます。
本処方は、裏寒や脾虚がある場合には不適となりますので、注意が必要です。
鑑別
三物黄芩湯と他処方との鑑別ですが、代表的なものに小建中湯、清心蓮子飲、滋陰降火湯、滋陰至宝湯があります。それぞれについて解説していきます。
小建中湯
三物黄芩湯と小建中湯は、共に手足の火照りが症状にあり、鑑別対象となります。
一言で言いますと、この2処方の違いは実熱か虚熱かの差になります。実熱なら三物黄芩湯、虚熱なら小建中湯になります。
小建中湯は疲れが溜まって顔が逆上せて、腹直筋緊張があり、手掌発汗等があるものに使用します。2~5歳の子供が丁度そんな感じですね。
三物黄芩湯の場合は地黄が入っていますので、胃腸が丈夫な方に使用します。また、小建中湯等に見られるような疲れはありません。その辺りで鑑別が可能となります。
-

【漢方:99番】小建中湯(しょうけんちゅうとう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
清心蓮子飲
三物黄芩湯と清心蓮子飲は、共に肺熱を清す処方であり、鑑別対象となります。
清心蓮子飲の特徴は、肺が渇いて胸に熱を持っている事です。勿論、心にも熱があり、また、泌尿器系のトラブルを抱えている事が多い処方でもあります。
三物黄芩湯は、その様な症状はまず出てきませんので、それで鑑別が可能となります。
-

【漢方:111番】清心蓮子飲(せいしんれんしいん)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
滋陰降火湯
三物黄芩湯と滋陰降火湯は、共に腎熱から肺熱を清す処方であり、鑑別対象となります。
この2処方は、共に腎熱を下す処方となります。しかし、滋陰降火湯には麦門冬が入っており、肺の乾燥と熱があるのが特徴です。
ですので、上の清心蓮子飲と同じ様に胸を触ると熱が解るのが特徴です。また、咳などの症状が出てくる場合もあります。
三物黄芩湯の場合、肺の渇きはありませんので、そのような症状は出てきません。その辺りで鑑別が可能となります。
-

【漢方:93番】滋陰降火湯(じいんこうかとう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
滋陰至宝湯
三物黄芩湯と滋陰至宝湯は、共に肺熱を清す処方であり、鑑別対象となります。
滋陰至宝湯の場合、その構成生薬に柴胡を含み、目つきが非常に鋭い印象です。また、清心蓮子飲や滋陰降火湯の様に肺の乾燥が顕著という特徴があります。
これらの所見は三物黄芩湯の場合にはありませんので、それで鑑別が可能となります。
-

【漢方:92番】滋陰至宝湯(じいんしほうとう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
お読み頂きありがとうございます。

以上です。少しでも参考になれば幸いです。以下より、他の漢方記事が検索できますので、宜しければご活用下さい。
-

「漢方薬の効果や副作用の解りやすい説明」データベース
続きを見る
-

目次
続きを見る