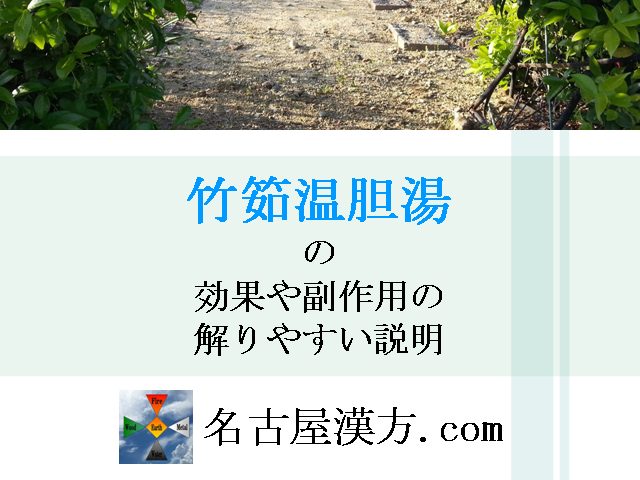
竹筎温胆湯
ポイント
この記事では、竹筎温胆湯についての次の事が解ります。
・患者さんへの説明方法、副作用や注意点
・出典(条文)、生薬構成
・詳しい解説、他処方との鑑別
「名古屋漢方.com」のムセキです。
本記事は、竹筎温胆湯についての解説記事になります。
最初に患者さんへの説明例、その後に詳しい処方解説を載せています。日々の業務で使う資料として、ご活用頂ければ幸いです。

スポンサーリンク
<急ぎの方用>患者さんお客さんへの説明

一般的な説明
今日は、竹筎温胆湯という漢方薬が出ています。このお薬は、風邪の中期に眠れないものにもよく使われています。
今日はどのような症状で受診されましたか?
○○という症状ですね。
お困りの症状に、先生はこれが良いと考えられたようです。このお薬は身体の循環を回復させて症状を改善しますので、一度、試してみてください。
身体が冷えたり、食欲が無くなりますと効き難くなりますので、体調には充分にお気をつけ下さい。
漢方医処方の場合の説明
今日は、竹筎温胆湯という漢方薬が出ています。このお薬は、不眠や不安が続く場合によく使われるお薬です。風邪の中期に眠れないものにもよく使われています。
今日はどのような症状で受診されましたか?
○○という症状ですね。
お困りの症状に、先生はこれが良いと考えられたようです。このお薬は身体の側面の循環を回復させて症状を改善しますので、一度、試してみてください。
胃腸の詰まりや上半身が熱くなる場合にも効いてきます。
身体が冷えたり、食欲が無くなりますと効き難くなりますので、体調には充分にお気をつけ下さい。
主な注意点、副作用等
アナフィラキシー
偽アルドステロン症
過敏症(発疹、蕁麻疹等)
冷え
添付文書(ツムラ91番)
ツムラ竹筎温胆湯(外部リンク)

竹筎温胆湯についての漢方医学的説明

生薬構成
半夏5、柴胡3、麦門冬3、茯苓3、桔梗2、枳実2、香附子2、陳皮2、黄連1、 甘草1、生姜1、人参1、竹筎3
出典
万病回春
条文(書き下し)
「傷寒にて日数過多してその熱が退かず、夢寐寧からず(むびやすからず:夢見が悪くて)、心驚恍惚、 煩躁して痰が多く眠らざる者を治す。」
条文(現代語訳)
「風邪をひいて何日が過ぎてもその熱が下がらず、夢見が悪くて、驚きやすくボーッとしていて、 悶えて痰が多く、眠らざる者を治します。」
解説
今回は、竹如温胆湯の処方解説になります。この処方は、一般的に風邪の中期以降において、眠れない場合によく使われます。
漢方専門の先生は、温胆(うんたん)の効能のある処方という事で、ストレスが身体に詰まっている事が原因で気が下がらないものに使用する場合もあります。
それでは、まずは条文を見ていきます。条文は、要約しますと「風邪中期の不眠や精神不安に使用する。」という意味になります。
また、竹筎温胆湯の名前にも入っている「胆」という文字は、五臓六腑の腑の一つである胆(たん)を指します。
名前から、胆が冷えて機能不全を起こしている状態なので、この処方で胆を温めてやればば良い、という事が読み取れます。
胆という臓器は「決断する」という機能を主るとされ、ここが機能不全になると「迷ってしまい、中々決断出来なくなる(どうしようか解らなくなる)。」状態になります。
「胆試し」、「胆が据わる」という言葉があります。
これらは胆の決断能力を表している言葉で、それぞれ「どんな状況でも落ち着いて決断出来るか?」「いつも動じない胆力を持っている。」という内容になります。
胆の機能不全が起こると、これらが出来なくなって迷います。
次に、構成生薬を見ていきます。構成生薬は、グループ分けしますと
利水・去痰:半夏、茯苓、生姜、桔梗
健胃:陳皮、甘草、人参、生姜
胃の鬱熱を取る:竹筎
潤肺:麦門冬
理気・破気:枳実、香附子、陳皮
疎肝:柴胡
清心:黄連
の様になります。かなり効果が分かれておりますが、肝心かなめの胆を温める生薬が入っていません。
ちょっと解りにくいのでもう少しまとめてみます。
竹筎温胆湯の効果は以下の5つになります。
①、肺の燥熱、心熱、胃熱を下す
②、痰を除いて健胃する
③、疎肝する事で上下の気の流通を復活させる
④、①②③と合わせて上焦に留滞している熱や気を下す
⑤、④の結果、胆が温まり足少陽胆経の流れが復活する
簡単に言いますと、足少陽胆経という経絡は身体の側面を走る経絡で、機能不全が起こると気が下がらなくなり、上焦に流れない気が溢れて熱を持ちます。
これが竹筎温胆湯証になります。
竹筎温胆湯は、その流れない気を何とかして下し、冷えている下部の足少陽胆経を温める事で胆を温めようという処方になります。
温胆という現象は、気が流れて初めて起こるとも言えます。胆が温まる事で、決断する力も復活します。
ちなみに、決断が出来ない時の所見としては「ああでもない、こうでもない。うーんうーん・・・。」と、こちらの問いかけに対して結論が出ない返答を繰り返します。
また、柴胡が入る事により、肝に熱がある事が解ります。つまり、胸脇苦満が出てきます。
以上をまとめますと、竹筎温胆湯は「風邪中期等で胸脇苦満等の肝に詰まりのある所見が有り、不眠不安を訴え、胆の冷えにより中々こちらの問いかけに対して返答をしない、決断できないもの。」に使用する処方と言えます。
本処方は、裏寒や脾虚がある場合には用いる事が出来ませんので注意が必要です。
鑑別
竹筎温胆湯と他処方との鑑別で、代表的なものに小柴胡湯、酸棗仁湯、柴胡加竜骨牡蛎湯があります。それぞれについて解説していきます。
小柴胡湯
竹如温胆湯と小柴胡湯は、共に風邪の中期の処方であり、鑑別対象となります。
両方、風邪をひいて暫く経った後、病邪が身体の中途半端な肝胆の位置に入り込んでしまっている状態です。
小柴胡湯の場合は往来寒熱といい、熱が出たり引っ込んだりするのが特徴で、時に吐き気や腹痛等の胃腸症状が出てくるのが特徴です。
竹筎温胆湯は、不眠症状や精神不安等の神経症状を主に出します。その辺りで鑑別が可能となります。
-

【漢方:9番】小柴胡湯(しょうさいことう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
酸棗仁湯
竹如温胆湯と酸棗仁湯は、共に不眠の処方であり、鑑別対象となります。
酸棗仁湯の場合、その根底に疲れがあり心血虚を引き起こしています。疲れこんで寝れないという事です。
ですので、柴胡の証である胸脇苦満がなく、胆の機能不全である「決断できない」という所見はありません。
これら2点が鑑別ポイントとなります。
柴胡加竜骨牡蛎湯
竹如温胆湯と柴胡加竜骨牡蛎湯は、共に不眠や精神不安に対する処方であり、鑑別対象となります。
両者共に、肝に熱があり、胃に詰まりがあって上焦に熱が溜まっている状態です。
相違点は、竹筎温胆湯の場合は肺熱があり、胃熱心熱の存在が挙げられます。逆に、柴胡加竜骨牡蛎湯は腎精の漏れがあり、それが原因で心腎交通が上手く行かない状態です。
竹筎温胆湯の場合は、解説の所でも取り上げました様に「自分で物事を決められない。」「はっきりとした返事をしない。」という特徴があります。
逆に柴胡加竜骨牡蛎湯はその様な所見は無く、胸脇苦満がしっかりと存在し、眼を見た時の違和感(中々表現し辛いのですが、「変わった目。」というイメージ)があるのが特徴です。
-

【漢方:12番】柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
お読み頂きありがとうございます。

以上です。少しでも参考になれば幸いです。以下より、他の漢方記事が検索できますので、宜しければご活用下さい。
-

「漢方薬の効果や副作用の解りやすい説明」データベース
続きを見る
-

目次
続きを見る