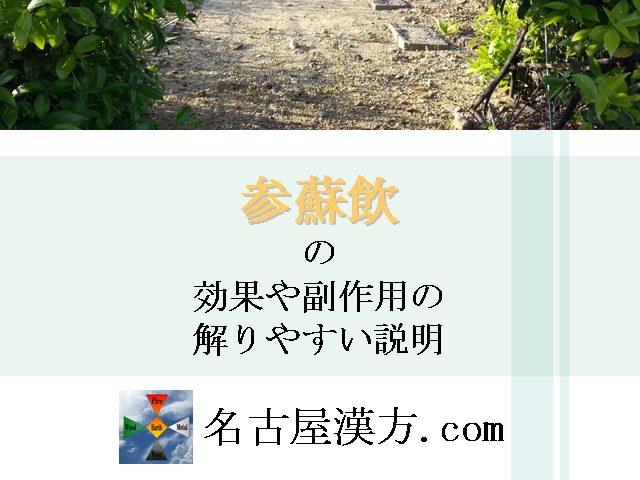
参蘇飲
ポイント
この記事では、参蘇飲についての次の事が解ります。
・患者さんへの説明方法、副作用や注意点
・出典(条文)、生薬構成
・詳しい解説、他処方との鑑別
「名古屋漢方.com」のムセキです。
本記事は、参蘇飲についての解説記事になります。
最初に患者さんへの説明例、その後に詳しい処方解説を載せています。日々の業務で使う資料として、ご活用頂ければ幸いです。

スポンサーリンク
<急ぎの方用>患者さんお客さんへの説明

一般的な説明
今日は参蘇飲という漢方薬が出ています。風邪薬で葛根湯というお薬がありますが、葛根湯の春夏バージョンみたいなお薬です。
今日はどうされましたか?
〇〇ですね。先生は、お困りの症状にこのお薬が合うと判断されたようです。痰が出る場合にも使えますので、一度飲んでみて下さい。
このお薬は、身体が冷えてくると効果が悪くなりますので、体調管理にお気をつけ下さい。
漢方医処方の場合の説明
今日は参蘇飲という漢方薬が出ています。一般的には、秋冬の寒い時期以外の風邪で、頭痛や発熱、痰が出る場合によく使われます。
今日はどうされましたか?
〇〇ですね。先生は、お困りの症状にこのお薬が合うと判断されたようです。葛根湯の様なお薬ですが、胃腸の不調があったり、咳痰が出る場合にも使えますので、一度飲んでみて下さい。
このお薬は、身体が冷えてくると効果が悪くなりますので、体調管理にお気をつけ下さい。
主な注意点、副作用等
アナフィラキシー
偽アルドステロン症
過敏症(発疹、蕁麻疹等)
冷え
添付文書(ツムラ66番)
ツムラ参蘇飲(外部リンク)

参蘇飲についての漢方医学的説明

生薬構成
半夏3、茯苓3、葛根2、桔梗2、陳皮2、大棗1.5、人参1.5、甘草1、枳実1、 蘇葉1、生姜0.5、前胡2
出典
和剤局方
条文(書き下し)
「感冒にて発熱頭疼(はつねつずとう)するを治す。あるいは痰飲凝結により、兼ねて以て熱を為すに並びに宜しく之を服すべし。」
条文(現代語訳)
「風邪にて発熱頭痛するものを治します。あるいは痰や水の滞りがあり、発熱を兼ねるものもこれを飲むと良いでしょう。」
解説
今回は参蘇飲の処方解説になります。
参蘇飲は、一般的にも風邪の処方として使われていますが、葛根湯や麻黄湯、香蘇散等に比べるとマイナーですので、漢方医の先生がよく使われるイメージがあります。
まず、条文を見ていきます。
和剤局方からの出典ですが、非常に簡単な文章となっています。内容は「風邪なら参蘇飲で治る。」と言った様な事しか書かれておりません。
次に、参蘇飲の構成生薬を見ていきます。構成生薬は、以下の様になっています。
理気:蘇葉
祛風湿熱:前胡
解肌・解表・発汗:葛根
排膿・去痰:桔梗
回水:茯苓
去痰・健胃:半夏、陳皮、人参、生姜
発表:生姜
胃部の破気・行気:枳実、陳皮
緩和・分散:甘草、大棗
色々と効能が多く解り辛く感じますが、この処方は葛根湯と対比する事で、理解しやすくなります。
-

【漢方:1番】葛根湯(かっこんとう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
葛根湯の構成生薬は、
解肌・解表・発汗:葛根、麻黄
桂枝:衛気を補う
芍薬:営気を巡らす
緩和・分散:大棗・甘草
健胃・発表:生姜
で、参蘇飲の方意が何となく似ています。しかも、葛根・大棗・甘草・生姜は両処方に存在しています。
この事より、参蘇飲の解析は、葛根湯を念頭に置いて行うとスムーズだと考えられます。
葛根湯においては、「表寒実」を改善する麻黄・葛根・桂枝であった部分が、参蘇飲では「風湿熱・気滞」を清する蘇葉・葛根・前胡・桔梗・枳実・陳皮となり、芍薬であった部分が、その手前において痰を除いて健胃する半夏・陳皮・人参・枳実となります。
茯苓は、その回水効果で、裏の気を上下に攪拌する作用があります。
これらをまとめますと、参蘇飲は「風湿熱が原因で起こる発熱頭痛で、ボーッとする等の気滞症状があり、胃が詰まって食欲が無く、痰が出るもの。」に用いる処方と言えます。
本処方は風湿熱の邪が原因となりますので、広義では温病に対する方剤にもなります。
そうしますと、「裏寒が無く、脾虚の軽いもので、春夏に起こりやすい発熱頭痛を伴う風邪」に適応出来る処方と言えます。簡単に表現しますと、「温病版葛根湯」ですね。
鑑別
参蘇飲と他処方との鑑別ですが、代表的なものに葛根湯(麻黄湯)、真武湯、清暑益気湯があります。
それぞれの処方について、鑑別方法をご紹介します。
葛根湯(麻黄湯)
参蘇飲は葛根湯を参考にして作られた形跡があり、鑑別対象となります。葛根湯や麻黄湯は、表寒実の薬になります。表とは体表、三焦ですと上焦を指します。
その部分が寒邪に侵されて、太陽膀胱経が首筋部分で詰まって発熱頭痛が起こります。
寒邪になりますので、皮膚を触ると全体的に冷たく、無汗、頭痛、発熱、首筋のコリ、場合により関節痛等が起こります。
葛根湯証や麻黄湯証は胃腸には問題がありませんので、咳痰は起こりません。その辺りでも鑑別が可能となります。
-

【漢方:1番】葛根湯(かっこんとう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
真武湯(温裏剤)
真武湯は「少陰の葛根湯」と呼ばれる事もあり、葛根湯証との鑑別が必要となりますが、参蘇飲の場合も同じ様に鑑別が必要となります。
上の解説の見出しでご紹介した通りですが、参蘇飲の使用条件には「裏寒が無い」事が前提になります。
手首足首の冷え、顔の中心が青黒い、壇中が冷たい、右下腹部ガス満等、裏寒所見があれば参蘇飲は不適になります。
その場合に真武湯をはじめとする温裏剤が適応となります。
-

【漢方:30番】真武湯(しんぶとう)の効果や副作用の解りやすい説明
続きを見る
清暑益気湯
清暑益気湯は、参蘇飲と同じく熱邪に侵された場合の処方であり、鑑別が必要となります。
清暑益気湯には、気虚の四君子湯や肺燥の生脈散が入り、胃腸の虚というのが一つポイントとなります。
元気が出ない、だるい、喉が渇く等の症状がメインで出てきます。ですので、参蘇飲の様な発熱や頭痛がメインという訳ではありません。
もし発熱、頭痛がありましても、夏バテや気虚様症状が強く出て来るようでしたら清暑益気湯を疑った方が良いでしょう。
お読み頂きありがとうございます。

以上です。少しでも参考になれば幸いです。以下より、他の漢方記事が検索できますので、宜しければご活用下さい。
-

「漢方薬の効果や副作用の解りやすい説明」データベース
続きを見る
-

目次
続きを見る