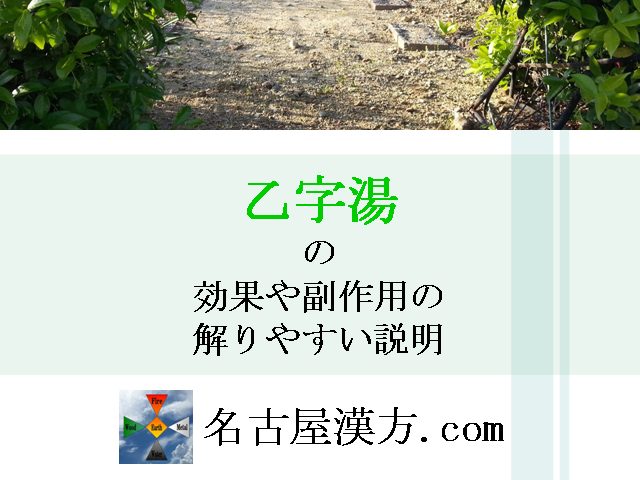
ポイント
この記事では、乙字湯についての次の事が解ります。
・患者さんへの説明方法、副作用や注意点
・出典(条文)、生薬構成
・詳しい解説、他処方との鑑別
「名古屋漢方.com」のムセキです。
本記事は、乙字湯の解説記事になります。
最初に患者さんへの説明例、その後に詳しい処方解説を載せています。日々の業務で使う資料としてご活用頂ければ幸いです。

スポンサーリンク
<急ぎの方用>患者さんお客さんへの説明

メイン
①痔の場合(他に例えば座薬や痔の塗り薬が出ている事多い。出ていなければ患者さん要確認。)
今日は漢方のお薬が出ていますね。乙字湯という名前です。痔の漢方薬としては一番よく使われる薬です。
大黄という生薬が少し便を柔らかくしますので、下痢に注意してください。多少柔らかくなる位なら問題ないですので、続けて下さいね。
あまりに緩くなるようでしたら、ご一報下さい。
このお薬は胃腸が弱ると効果が出にくいので、刺激物を避けて、胃腸にやさしい食事を心がけて下さい。また、ストレスもなるべく少なくなるように、早く寝て頂くと早く良くなりますよ。
②目的が痔の治療ではない場合(漢方医の場合は、痔以外の使い方をする場合もあります)
今日は乙字湯という薬が出ています。一般的には痔の薬として有名です。
今回は、痔ではないとのことですが、こちらの処方が出ています(この言葉が無いと、「痔じゃないのに!」と返されます)。
この薬は、生薬の構成から、下っ腹の「お血」という毒を取るような構成になっています。
ですので、漢方的には痔だけではなく、今回のような病気にも使う事があります。
このお薬は胃腸が弱ると効果が出にくいので、刺激物を避けて、胃腸にやさしい食事を心がけて下さい。
また、ストレスもなるべく少なくなるように、早く寝て頂くと早く良くなりますよ。
主な注意点、副作用等
アナフィラキシー
偽アルドステロン症
肝機能障害
間質性肺炎
血圧上昇
胃腸障害(脾虚)
下痢
冷え(裏寒)
添付文書(ツムラ3番)

葛根湯についての漢方医学的説明

生薬構成
当帰6、柴胡5、黄芩3、甘草2、升麻1、大黄0.5
出典
水戸藩の侍医である原南陽の著書「叢桂亭医事小言(そうけいていいじしょうげん)」より
条文(書き下し)
「痔疾、脱肛痛楚し、あるいは下血腸風し、あるいは前陰痒痛するものを理する方。」
条文(現代語訳)
「痔疾患で、脱肛し酷く痛み、あるいは下血して、あるいは前陰が痒痛するものを治す薬。」
解説
乙字湯は面白い処方で、升麻と柴胡の組み合わせで昇提作用があります。
この組み合わせで有名なものに「補中益気湯」があり、乙字湯はそれと同じく落ち込んだ臓を上に引っ張り上げる作用があります。
そして、黄芩と大黄で、余分な熱と毒を取ります。柴胡が入っていますので、眼付きの鋭い神経質な方に向いています。
処方中に人参や白朮と言った生薬が入っていませんので、脾虚がある場合には使用不可となります(裏寒も×)。
前陰痒痛するもの、と条文にある通り、小児の陰部掻きむしりにも使用出来ます(大黄の量は少ないので、便の様子を見ながら長服可能)。
私が経験した使用法として、偽膜性大腸炎やクローン病に乙字湯を使って奏功した例があります。
処方中の当帰は、血を温める作用があり、活血というお血の除き方をします。この対象にある生薬が牡丹皮です(大黄牡丹皮湯等)。
乙字湯は、服用期間が長いと冷え(裏寒)や胃腸障害(脾虚)が起こる可能性がありますので、注意が必要です。
乙字湯以外にも、甲字湯、丙字湯、丁字湯と創方されています。
お読み頂きありがとうございます。

以上です。少しでも参考になれば幸いです。以下より、他の漢方記事が検索できますので、宜しければご活用下さい。
-

「漢方薬の効果や副作用の解りやすい説明」データベース
続きを見る
-

目次
続きを見る